
目次
アレルギー性鼻炎の診断と適切な対応
鼻水が続くだけでアレルギー性鼻炎と診断してはいけない
鼻水が続いているからといって、すぐにアレルギー性鼻炎と診断するのは適切ではありません。季節性(花粉の飛散時期)や環境要因(ハウスダスト、ダニなど)との関連を考慮する必要があります。
特に子どもは風邪を繰り返しやすく、鼻水が続いているように見えることがあります。そのため、安易にアレルギー性鼻炎と診断されることが少なくありません。成人でも、環境の変化や体調によって一時的に鼻炎の症状が出ることがあり、慎重な診断が求められます。
アレルギー性鼻炎とは
アレルギー性鼻炎は、ハウスダストや花粉などの刺激により鼻の粘膜が反応して起こる疾患です。症状として鼻水、鼻づまり、くしゃみなどがあり、日常生活に支障をきたすことがあります。学業や仕事に集中できなくなったり、夜間の鼻づまりで睡眠の質が低下することもあります。
風邪と症状が似ているため、単なるウイルス感染による鼻炎との区別が重要です。特に子どもは集団生活で風邪を繰り返すことが多いため、鼻水が長引いていても必ずしもアレルギー性鼻炎とは限りません。
透明な鼻水が続く場合に考えられる疾患

透明な鼻水やくしゃみ、鼻づまりがある場合、以下の疾患が考えられます。
- 急性鼻炎(風邪によるもの)
- アレルギー性鼻炎(花粉症など)
- 血管運動性鼻炎(温度差などで自律神経が影響を受けて発症)
- 好酸球増多性鼻炎(アレルギー検査は陰性だが、鼻水中に好酸球が増加)
- 職業性鼻炎(化学物質や粉塵などによる刺激性鼻炎)
これらを正しく鑑別するためには、問診・診察・検査を行い、原因を特定することが重要です。
アレルギー性鼻炎の診断基準

アレルギー性鼻炎の診断には、以下の基準が用いられます。
- 鼻水中の好酸球の増加
- 抗原特異的IgE抗体検査または皮膚試験の陽性
- 鼻粘膜抗原誘発試験の陽性(くしゃみ、鼻のかゆみ、鼻粘膜の腫れなどが確認される)
子どもや検査が難しい場合は、①と②を中心に診断を行います。また、日常生活での症状のパターンを詳しく把握することも重要です。
アレルギー性鼻炎の特徴と診断の流れ
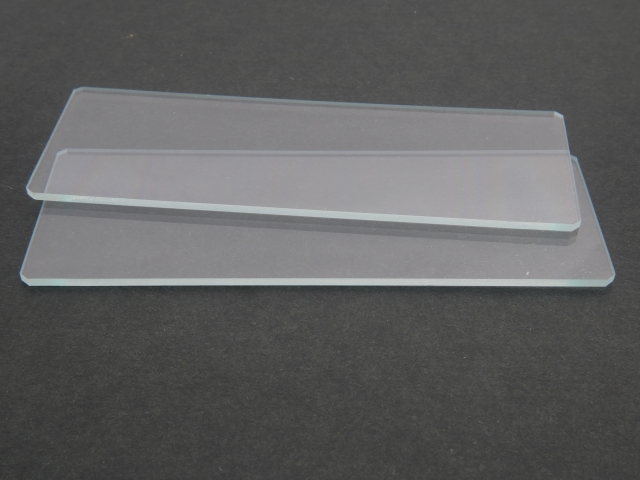
アレルギー性鼻炎の特徴として、以下の点が挙げられます。
- 通年性の鼻炎が多い(ハウスダスト、ダニなどによる影響)
- 自然に治ることが少ない
- 喘息や副鼻腔炎を合併しやすい
- 症状の表現が曖昧になりやすい(特に子ども)
診断の流れは次のとおりです。
- 問診(症状の発症時期、環境要因、家族歴、アレルギー歴などを確認)
- 鼻鏡検査(鼻粘膜の状態を観察)
- 鼻汁好酸球検査、血液検査または皮膚試験、鼻粘膜抗原誘発試験
- 診断後、治療開始または経過観察
問診で確認するポイント
- 鼻水が出るタイミング(季節性や時間帯)
- 温度差や環境変化による影響
- 風邪をひいていないか
- 家族にアレルギー疾患があるか
- 喘息や食物アレルギーの既往
これらを医師に伝えることで、より正確な診断につながります。
アレルギー性鼻炎の検査方法
- 鼻粘膜の観察(アレルギー性鼻炎では粘膜が青白く腫れる)
- 鼻汁好酸球検査(風邪との鑑別に有効)
- 皮膚反応検査(抗原特定のための検査)
- 血中特異的IgE抗体検査(採血によるアレルギー診断)
- 鼻粘膜誘発試験(抗原を鼻粘膜に作用させ、症状を確認)
子どもに適した検査は、鼻汁好酸球検査、皮膚反応検査、血液検査が主になります。
治療と予防
アレルギー性鼻炎の治療では、まず抗原との接触を避けることが重要です。生活環境の改善を指導し、それでも症状が続く場合は薬物療法を行います。治療を開始する際には、薬のメリットとデメリットを十分説明し、必要最低限の使用に留めることが大切です。
まとめ
近年、アレルギー性鼻炎の患者数は増加していますが、「鼻水が続いている=アレルギー性鼻炎」と即断するのは危険です。風邪やその他の鼻炎としっかり区別し、適切な診断を行うことが重要です。医療従事者だけでなく、患者やその家族も正しい知識を持ち、必要な治療を受けることが大切です。






